
腎機能と減塩を看護と国試に活かす|臨床で実践できる基礎知識

看護学生・新人ナース向けに、勉強法・実習・キャリアなどの情報を発信する専門メディアです。
現場で活躍する看護師のインタビューや、国家試験対策に役立つ記事が豊富。
「勉強だけでなく、将来の働き方も知りたい」方におすすめです。
 学生さん
学生さん腎機能が低下すると、どうして減塩が必要なの?



私も腎臓と減塩の関係を整理できず、実習先で質問されて困った経験がありました。
多くの看護学生は、腎機能と減塩のつながりに不安を抱えています。
授業で習っても、なぜ必要なのか根拠を説明できるまで理解するには、アウトプットも大事です。
腎機能と塩分制限は、eGFRやクレアチニンなどの検査値、慢性腎臓病(CKD)の食事療法に関連する設問が国家試験に登場しています。
理解が不十分だと、国家試験の得点や、実習での患者対応にも影響してしまいます。
- 腎臓が担う水分・電解質調整の役割
- 塩分摂取が血圧や腎機能に及ぼす影響
- 腎機能低下時に減塩が必要となる理由
- 看護における減塩指導の目安と具体的な工夫
- 国家試験で問われる腎機能と減塩の出題例
国家試験の学習だけでなく、臨床実習や将来の患者指導に活かせる力を養うために、腎機能と減塩の関係を一緒に整理していきましょう。
腎機能と塩分の関係
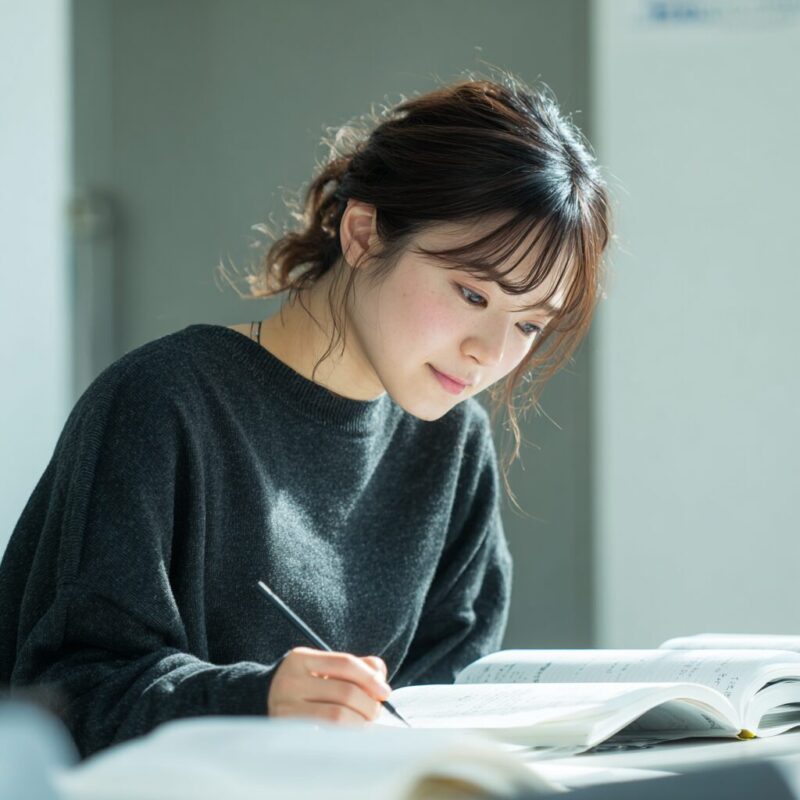
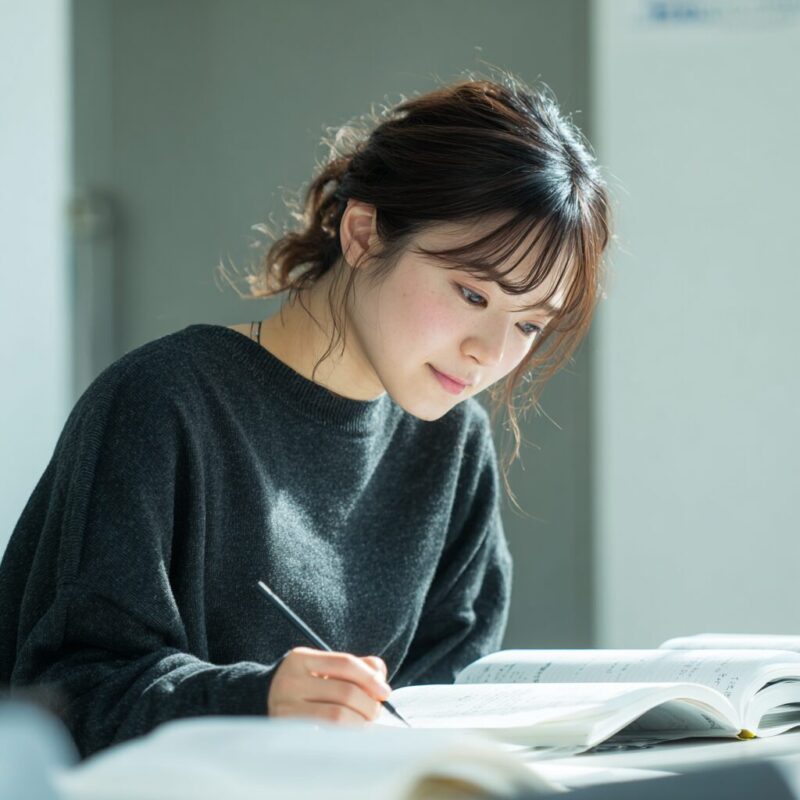
腎臓は「体のろ過装置」として老廃物を処理したり、体液量や血圧を調整したりします。
ナトリウム(塩分)は、水分と結びつき体内の水分量と電解質のバランスを左右するため、腎臓の働きを考えるうえで重要です。
腎臓の基本的な役割を整理し、塩分摂取が体に与える影響を確認しましょう。
腎臓が担う水分・電解質調整の役割
最初のポイントは「ナトリウム再吸収=血圧上昇」「ナトリウム排泄=血圧低下」の関係をおさえましょう。
腎臓は尿をつくる過程で、体内の水分やナトリウム・カリウムなどの電解質を調整します。
血液は糸球体でろ過された後、尿細管で必要な成分が再吸収されます。
ナトリウムの再吸収と血圧は、次の流れで変動します。
| 血圧上昇 | 血圧低下 |
|---|---|
| 1.ナトリウム再吸収 2.浸透圧で水分も一緒に吸収 3.血液量が増加 4.血圧上昇 | 1.ナトリウム排泄増量 2.水分量も排泄 3.血液量が低下 4.血圧低下 |
腎臓は、体液量や電解質バランスを一定に保ち、生命維持に欠かせない役割を果たします。
塩分過剰摂取が与える影響
塩分の過剰摂取は、高血圧と腎機能低下の要因につながります。
塩分を多く摂取すると、糸球体でのろ過が追いつかずナトリウムが体内に蓄積します。
ナトリウムの蓄積は、血液量の増加を引き起こし血圧を上げます。
高血圧が続くと腎臓の糸球体に強い圧力がかかり、濾過機能が徐々に損なわれ腎機能が低下につながるのです。
塩分の過剰摂取による体への影響を理解すると「なぜ減塩が必要なのか」が見えてきます。
病態の流れを整理して看護や実習に臨みましょう。



減塩は腎臓や体全体を守る大切な習慣です。
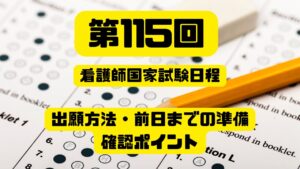
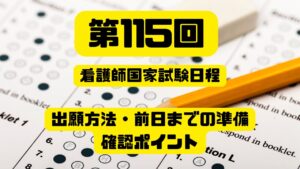
腎機能低下と減塩の必要性


減塩は、腎機能を守るために欠かせない食事療法です。
国家試験でも繰り返し出題される内容であり、実習や臨床での生活指導にも直結します。
腎機能低下を引き起こす主な腎臓病
国家試験に出題されやすい、代表的な腎臓病を整理しましょう。
- IgA腎症:糸球体腎炎。血尿や蛋白尿が特徴で進行すると慢性腎不全へ移行
- 慢性腎臓病(CKD):腎機能低下や蛋白尿が3か月以上続く状態。高血圧や糖尿病が主要な原因。
- 糖尿病性腎症:糖尿病の三大合併症のひとつ。腎不全へ移行し透析が必要になることが多い
- 急性腎障害(AKI):急激に腎機能が低下する病態。脱水、ショック、薬剤などが主な原因
- ネフローゼ症候群:大量の蛋白尿(3.5 g/日以上)、低アルブミン血症、浮腫、高脂血症が特徴
いずれも腎機能の低下を引き起こし、進行予防や症状緩和のために減塩が重要です。
腎臓病における減塩効果
腎臓病では、腎機能低下や腎臓への負担を軽減させるために、減塩が重要です。
減塩には、以下の効果があります。
- 血圧の安定化:ナトリウムの再吸収を抑えることで血圧が下がり、腎臓への負担が軽減する。
- 尿蛋白の減少:糸球体の圧力が和らぐことで、尿蛋白の排泄が減少する。
ガイドラインでは慢性腎臓病患者の塩分摂取量を1日6 g未満と推奨しています。
厚生労働省の調査によると日本人の平均摂取量は10 g前後であり、日常生活習慣の改善は容易ではありません。
看護師は患者さんの生活習慣を理解し、現実的な減塩方法を一緒に考える必要があります。



本人の他に食事を準備したり、サポートしたりする家族にも協力を得て、具体的な工夫を伝えることが大切です。


減塩指導の看護ポイント


看護師は、患者さんの生活背景や食生活を理解しながら、日常生活に取り入れられる減塩方法を一緒に考えることが大切です。
臨床でのアセスメントや、塩分摂取量の目安、実践しやすい減塩の工夫などを整理します。
減塩指導前に行う情報収集とアセスメント
減塩指導を行う際は、患者さんの検査値や生活習慣、環境などを含めた情報収集とアセスメントが必要です。
- 家族全体の食事スタイル(濃い味付けを好むかどうか)
- 外食やコンビニ食の利用頻度
- 経済状況や調理環境
- 減塩の重要性に対する理解度と意欲
患者さん一人では、習慣を変えたり減塩を続けたりするのは、心理的に難しい場合があります。
家族や周囲の協力者を巻き込んだ生活習慣の指導をすると、現実的で継続可能な支援につながります。



患者さんの年齢や家族構成など、生活背景をふまえて“一緒にできる工夫”を考えましょう。
1日の塩分摂取量の目安と指導内容
減塩指導を伝えるときには、患者さんがイメージしやすく行動しやすい具体的な行動を示しましょう。
- 味噌汁を摂取回数を減らす
- 漬物や梅干しの量を控える
- 加工食品やインスタント食品の頻度を下げる
- 調味料は「かける」より「つける」で摂取量を減らす
- 出汁や香辛料を活用する
減塩は面倒に感じますが、患者さんが楽しみにしている生活習慣を尊重したアドバイスをすると、取り入れやすいです。
実践しやすい減塩の工夫
腎機能に関わらず、減塩は日頃から意識することで身体への負担軽減に繋がります。
減塩を手軽に長く、続けるためには、以下のような小さな工夫の積み重ねが効果的です。
- レモンや酢など酸味を使って味にアクセントをつける
- 麺類の汁を残す
- 減塩しょうゆや減塩みそを利用する
- 食卓に調味料を置かず、調理の段階で味を調整する
患者さんに受け入れられやすい「今日からできる工夫」を示すことで、減塩が継続しやすくなります。
日頃から、腎臓に負担をかけない優しい日常生活を発信できる看護師さんは、今後も重宝されます。
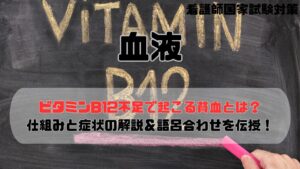
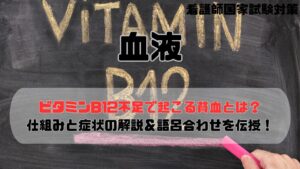
ケアナス(CareNurse)は現場で働く先輩ナースの体験談や、学習に役立つリアルな情報が分かりやすくまとめられています。
勉強だけでなく、将来の働き方に不安を感じている方におすすめです。
看護師国家試験で問われる腎機能と減塩


国家試験の出題形式は「生活指導の適切な内容を選ぶ」「腎機能検査値と食事療法を関連づける」といった形が見られます。
過去問を確認し、どのように問われているのかを整理しましょう。
問題に触れることで、学習すべきポイントが明確になります。
第108回(2019年)午後49問
Aさん(76歳、女性)は、ステージ2の慢性腎臓病と診断された。身長146 cm、体重50 kg。日常生活は自立し、毎日家事をしている。週2回、ビールをグラス1杯程度飲んでいる。
Aさんへの生活指導の内容で優先されるのはどれか。
- 安静
- 禁酒
- 減塩
- 体重の減量
答え
3.減塩
【解説】
腎臓病では、塩分の6 g/日未満の制限が必要です。
第98回(2009年)午前112問
次の文を読み問題に答えよ。
4歳の男児。3、4日前から活気がなく、眼瞼と下腿の浮腫に母親が気付き来院した。血液検査の結果、総蛋白3.7 g/dL、アルブミン2.1g/dL、総コレステロール365 mg/dL、尿蛋白3.5 g/日で、ネフローゼ症候群と診断され入院した。入院時、体重18.0 kg。尿量300 mL/日、尿素窒素12 mg/dL。
問題
入院時の食事で制限するのはどれか。
- 塩分
- 糖質
- 脂質
- 蛋白質
答え
1.塩分
【解説】
ネフローゼ症候群では、塩分や水分の制限が必要とされます。
第105回(2016年)午前95問
次の文を読み問題に答えよ。
Aさん(34歳、男性)は、運送会社で配達を担当している。6か月前の職場の健康診断で、血圧142/90 mmHgと尿蛋白2+、尿潜血2+を指摘されたが放置していた。1週前、感冒様症状の後に紅茶色の尿がみられたため内科を受診した。血清IgAが高値でIgA腎症が疑われ入院した。
問題
AさんはIgA腎症と診断され、塩分1日6 gの減塩食が開始された。入院前は塩辛いものが好物で外食が多かったAさんは「味が薄くて食べた気がしない。退院後も続けられるかな」と話している。
このときの対応で最も適切なのはどれか。
- 「つらいですが慣れてきます」
- 「最初に甘いものを食べてください」
- 「各食事で均等に塩分を摂取しましょう」
- 「酸味や香味を利用するとよいでしょう」
- 「市販のレトルト食品は塩分が少ないので活用するとよいです」
答え
4.酸味や香味を利用するとよいでしょう
【解説】
腎臓病では塩分制限が必要ですが、酸味や香味の制限はありません。塩分を制限しつつもおいしく感じられる工夫を提案しましょう。
第103回(2014年)追試 午前96問
次の文を読み問題に答えよ。
Aさん(65歳、女性)は、20年前に糖尿病と診断されて血糖降下薬の服用を開始した。15年前から微量アルブミン尿が出現し、腎機能は徐々に悪化してきていた。10年前からインスリン療法を開始している。Aさんは外来受診時に、全身倦怠感と下肢の浮腫が認められ、精査加療目的で入院した。入院時は、身長155cm、体重65 kg(1か月で5 kg増加)、体温36.3℃、呼吸数28/分、脈拍82/分、血圧160/82 mmHgであった。Aさんの血液検査データは、Hb8.5 g/dL、HbA1c8.5%、アルブミン3.1 g/dL、クレアチニン3.5 mg/dL、K4.0 mEq/Lで、糸球体濾過量〈GFR〉は11 mL/分/1.73 m2であった。
問題
Aさんは、症状が改善したため、透析は導入しないで栄養指導を受けて退院する予定である。Aさんの食事療法で適切なのはどれか。
- 塩分は6 g/日未満とする。
- 水分は2,000 mL/日とする。
- 蛋白質は1.2 g/kg/日とする。
- 総エネルギーは50 kcal/kg/日とする。
答え
1.塩分は6g/日未満とする。
【解説】
腎臓病患者の食事療法では、塩分制限の他に、水分・蛋白・カリウムの制限などが必要になる場合もあります。



国試の選択肢は、実際の臨床に直結していることが多いです。
問題を解くときに“現場ではどう説明できるか”と考えると、理解が深まり患者指導にも役立ちます。
国試と臨床に活かせる腎機能と減塩の知識
腎機能と減塩の関係は、国家試験と臨床現場で重要なテーマです。
腎臓は体液量や電解質のバランスを調整する臓器であり、ナトリウム摂取が血圧や腎臓の働きに影響を与えます。
- ナトリウムの排出が増えると血液量が低下し、低血圧になる
- ナトリウム吸収が増えると血液量が増加し、高血圧になる
腎機能が低下するとナトリウム排泄が困難になり、高血圧と腎障害の悪循環が進行します。
悪循環を断ち切るために、減塩は欠かせません。
減塩指導は、患者さんの生活環境や習慣を情報収集し、実現可能な具体的なアドバイスが重要です。
家族や周囲の人に協力してもらい、減塩生活を継続できる環境を整えましょう。
国家試験では「減塩により血圧上昇を防ぎ、腎機能を保護する」構造が問われます。
腎機能と減塩、血圧との関係視点をもって国家試験対策をしましょう。



減塩と腎機能の関係を理解して、試験に合格する読解力と、患者さんを支える力を身につけましょう。
国家試験の勉強をしていると、知識の整理だけでなく「現場でどう活かすか」も気になりますよね。
ケアナス(CareNurse)では、先輩ナースの就職・転職経験談などの情報が無料で読めます。
勉強の合間に読むだけでも、視野が広がります✨
試験勉強、頑張ってくださいね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



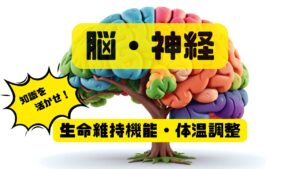
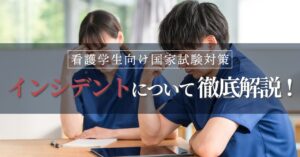
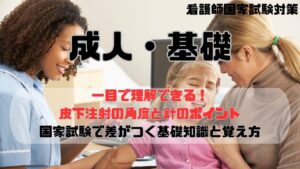
コメント