
看護師はインシデントが怖い?徹底理解!国試と現場で活きる基礎知識&過去問解説

 学生さん
学生さんインシデントってヒヤリ・ハットと同じなんですか?報告は必要だって聞くけど、違いがよくわかりません。



国家試験でも出るし、実務でも大事だって言われるけど、報告したら怒られそうで怖いです。



インシデント報告は「怖いもの」「責められるもの」と思われがちですが、実は患者さんを守り、自分自身を守るために大切な仕組みです。
インシデントは、現場で起きた問題をチームや多職種で共有し、再発防止のために重要です。
問題を起こした人を問うのではなく、今後の課題を見つけるきっかけになります。
現場に出てからも必ず関わる内容であり、責められる怖さを優先せずに、安全を守るために必要な行動だと理解しましょう。
- インシデントの定義と分類
- インシデント報告が大切な理由
- 現場での報告・対応のポイント
- 医療安全管理者の役割
- 国家試験の出題ポイントと過去問解説
インシデントの正しい知識を身につけることで、安心して実務に臨めるようになります。
一緒にしっかり学んで、国家試験合格と安全な看護実践を目指しましょう!
\卒業旅行はやっぱり海外でしょ/
卒業旅行は、先に決めておくのがおすすめです。予約やプランの決定など、決めることが多いことも…でも、勉強を頑張るモチベーション維持には大活躍です!
インシデントとは?基本をおさえよう


ここでは、インシデントの定義と分類を整理して解説します。
インシデント類の定義や具体例
インシデントとは、医療現場や看護業務において「事故や医療過誤にまでは至らなかったが、ミスや問題が発生した事例」を指します。
- 誤った薬剤を準備したものの投与前に気づいた
- 患者に実施されたが、結果的に患者へ傷害・不利益を及ぼさなかった
ヒヤリ・ハットは、重大事故の一歩手前で危険を感じたが、事故には至らなかった事象を指します。
- 薬剤投与の前にラベルを確認し、違う薬だと気付いた
- 患者さんが廊下の歩行練習中に、停めてあった車椅子に引っかかり、つまずいた
アクシデント(医療事故)は、実際に患者に傷害や不利益が発生した重大な事故を意味します。
- 誤薬投与により低血圧を起こし、治療が必要になった
- 検査前の薬を、違う患者さんに飲ませてしまい、検査予定の患者さんは検査を受けられなかった
インシデントが実際に発生したのか、していないのかで、区分することを念頭にいれましょう。
インシデントの分類
インシデントは患者への影響度によってレベル分けされます。
レベルは0~5まであり、代表的なレベル分けは以下のとおりです。
| レベル | 障害の継続性 | 障害の程度 | 代表例 |
|---|---|---|---|
| 0 | なし | なし | エラーがあったが患者には実施されなかった (ニアミス) |
| 1 | なし | なし | エラーが患者に実施されたが実害なし |
| 2 | 一過性 | 軽度 | 軽度のバイタル変化 処置不要・観察のみ |
| 3a | 一過性 | 中等度 | 簡単な処置(鎮痛剤投与、消毒など)が必要 |
| 3b | 一過性 | 高度 | 人工呼吸器装着、手術、入院延長などが必要 |
| 4a | 永続的 | 軽度〜中等度 | 永続的障害があるが機能障害や美容上問題は小さい |
| 4b | 永続的 | 中等度〜高度 | 永続的障害があり、機能障害・美容上の問題が大きい |
| 5 | 死亡 | 死亡 | 患者が死亡(原疾患の自然経過を除く) |
- インシデント =「事故や医療過誤に至らなかったが、ミスや問題が起きた事例」
- レベル0〜3a がインシデント、3b〜5 がアクシデント



インシデントの分類をしっかり理解して正しく報告・共有することで、迅速な対応と再発防止につながります


なぜインシデントが大切なの?


インシデント報告は、安全な医療を提供するために欠かせない取り組みです。
ここでは、なぜ報告や共有が大切なのか整理します。
患者さんの安全を守るため
小さなインシデントでも報告して共有することが重要です。
スタッフ間で、インシデント情報を共有すると問題認識がうまれるため、同じミスを引き起こす予防になります。
具体的な対策は、患者さんの環境整備やスタッフの業務見直しなどに活かされます。



ミスが起こりやすい環境を整えることで、 一人ひとりの「気づき」が患者さんの命を守る力になります。
組織全体の成長と信頼構築
インシデント報告は、組織全体の成長に繋がるきっかけになります。
医療は日々進歩しているため、10年前と現在では使用する機材や人も変化します。
便利な機材でも使用方法を間違える可能性があり、インシデント報告を通して、マニュアルの見直しのきっかけにつながるのです。



組織全体で成長し、仕組みを見直し、患者さんやご家族からの信頼につながります。
自分自身を守るため
報告を通して自分の行動を振り返り、今後の改善や成長につなげます。
誰しも人間、インシデントを起こすリスクはありますが、予防対策も可能です。
そのために、ダブルチェックで確認する人数を増やしたり、チェック表を使用して情報共有したりすると、インシデントのリスクが下がります。
チーム全体で情報を共有し、問題が起こらないように協力し合うことで、組織全体の安全体制を強化できます。
報告は「個人を守る」だけでなく、チーム全体でインシデントを予防するための大切なステップです。



私も新人の頃は報告するのが怖かったです。
でも勇気を出して報告したら、インシデントは自分だけの問題じゃないんだって気づきました。
報告は患者さんも自分自身も守るための大事な仕事の一つです。


現場での対応ポイント


インシデントが起きてしまったときは、焦らずに適切な対応が求められます。
ここでは、現場で実践できる基本的な対応ポイントを整理します。
迷わず速やかに報告する
インシデントが起きたら、患者さんの安全を最優先に行動し、状況を確認します。
状況次第では、スタッフの応援を呼んで患者さんの安全を最優先します。
状況を確認した後は、チームリーダーや上司、担当医師などに報告です。
チームリーダーは、全体の状況を把握しインシデント内容の共有を行い、注意喚起を広めます。
主任や師長は、医療安全管理者と連携し原因の特定や対策を講じます。
医師には、インシデント発生で患者さんがどういう状況になったのか報告し、必要があれば指示を仰ぎます。



報告は、患者さんの状態を正確に共有し、迅速に最適な対応をとるために必要です。
患者さんへの説明と配慮
インシデントは、患者さんやご家族への説明が必要です。
説明では、専門用語を避け、わかりやすい言葉で誠意をもって伝えることが大切です。
- 発生した時刻
- インシデントの状況
- 現在の患者さんの状態
- 医師の指示内容
- 今後の対応策
状況と対策を丁寧に説明し、不安を和らげる配慮をします。
説明後は、患者さんと家族は再発を危惧する方が多いです。
説明した対策を徹底し、患者さんと家族に再発予防を実施し安心を提供することが重要です。
再発防止策を考える
インシデントの原因を分析し、なぜ起きたのかを振り返ります。
そのうえで、以下のような具体的な対策が求められます。
- ダブルチェックのタイミングを見直す
- 看護師経験年数や病院勤務歴の組み合わせを考慮する
- 指差し呼称や声出し確認を徹底する
- マニュアルやルールの曖昧さを改善する
- 環境(配置・動線・物品の位置など)を整理する
指差しや声出し確認は、薬剤であれば服用タイミングや種類、目的、投与方法など、重要なタイミングで行います。



「どうしたら同じことが起きないか」をチーム全員で話し合い、現場に合わせた改善策が重要です。
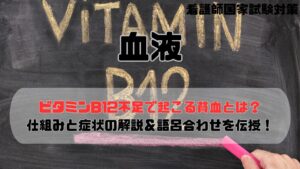
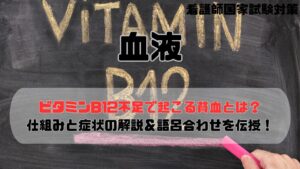
医療安全管理者について知っておこう!


医療安全管理者は、すべての医療スタッフが安心して患者さんに向き合えるように、現場の安全対策を計画・指導・改善する役割を担う専門職です。
仕組みづくりや教育を通じて現場を支えているため、役割を理解しておくことは、チーム医療を実践するうえで欠かせません。
さらに、医療安全管理者に関する国家試験が出題される可能性もあるため、今のうちに学んでおきましょう。
医療安全管理者とは
医療安全管理者とは、「各医療機関の管理者から安全管理のために必要な権限の委譲と、人材、予算およびインフラなど必要な資源を付与されて、管理者の指示に基づいて、その業務を行う者」と定義されています。
引用元:厚生労働省ホームページ
役割は、病院全体の安全対策をリードし、医療事故の予防やインシデントの分析、現場の課題抽出などを通して、安全を高める中心的存在です。
医療安全管理者になるために特別な資格は必要ありませんが、医療現場での実務経験や医療安全に関する知識が求められます。



外部研修の受講が条件となる場合もあり、経験とスキルの両面が重視されます。
医療安全管理者の具体的な業務内容
医療安全管理者の具体的な業務内容には、以下のようなものがあります。
- インシデントやアクシデントの報告を取りまとめる
- 原因分析を行い、再発防止のための改善策を立案する
- 医療安全に関する研修や教育の企画・実施を担当する
- 病院内のマニュアルや手順を作成・見直す
- 新人スタッフへの安全教育や現場での指導を行う
例えば、与薬ミスが多い部署があれば、業務プロセスを見直したり、ダブルチェック体制の強化を進めたりするなどの対応を行います。



『安全な医療を提供する』という共通の目標を実現するために、多職種と連携して取り組む、現場の安全を支える要のような存在です。


インシデントの看護師国家試験での出題傾向について


インシデントに関する看護師国家試験で問われるポイントは、以下の通りです。
- インシデントの定義と分類
- 報告の目的と重要性
- 現場での具体的な対応方法
- 医療安全管理者との関連
「状況設定問題」や「チーム医療における役割分担」を通して、単なる知識だけでなく、現場での判断力や考え方が問われるケースが増えています。



国家試験では「なぜそうするのか?」という理由を理解して答えることがポイントです。


国家試験の過去問と解説


インシデントに関する、実際に出題された問題を確認しましょう。
第98回 午後42問
インシデント(ヒヤリ・ハット)報告の目的はどれか。
- 反省
- 謝罪
- 責任追求
- 原因究明
答え
4.原因究明
解説
インシデント報告の目的は、事実を共有し再発防止につなげるための「原因究明」です。
責任を追及するためではなく、事故を未然に防ぐための重要な取り組みです。
第109回 午後74問
与薬の事故防止に取り組んでいる病院の医療安全管理者が行う対策で適切なのはどれか。
- 与薬の業務プロセスを見直す
- 医師に口頭での与薬指示を依頼する
- 病棟ごとに与薬マニュアルを作成する
- インシデントを起こした職員の研修会を企画する
答え
1.与薬の業務プロセスを見直す
解説
業務プロセスを見直すことで、事故の原因を構造的に改善できます。
口頭指示の依頼(選択肢2)は聞き間違いリスクが高く、病棟別のマニュアル作成(選択肢3)は全体統一性が損なわれる恐れがあります。
インシデントを起こした職員のみの研修(選択肢4)は懲罰的になりやすく、事故防止に効果的とは言えません。
第113回 午後89問
インシデントレポートについて適切なのはどれか。2つ選べ。
- 法令で書式が統一されている
- 責任追及のためには使用されない
- インシデントの発生から1か月後に提出する
- 分析結果は他職種を含めて組織全体で共有する
- 患者に実施される前に発見された誤りの報告は不要である
答え
2.責任追及のためには使用されない
4.分析結果は他職種を含めて組織全体で共有する
解説
インシデントレポートは責任追及が目的ではなく、再発防止のために活用されます(選択肢2)。
また、分析結果は他職種を含めて組織全体で共有し、安全文化を強化します(選択肢4)。
書式は法令で統一されておらず(選択肢1)、発見が早くても報告は必要です(選択肢5)。
第114回 午後73問
医療安全について正しいのはどれか。
- 患者から暴力を受けた医療従事者に暴力発生の責任を問う
- 与薬前に薬物の間違いに気づけばインシデントレポートは不要である
- 医療過誤とは医療事故の原因に医療従事者の過失がある場合をいう
- インシデントを起こした医療従事者は数日後にレポートを提出する
答え
3.医療過誤とは医療事故の原因に医療従事者の過失がある場合をいう
解説
医療過誤とは、医療事故の原因に医療従事者の過失がある場合を指します(選択肢3)。
報告はすぐに行い(選択肢4は誤り)、間違いに気づいた場合でも報告が必要です(選択肢2は誤り)。
医療従事者に暴力の責任を問うことは不適切です(選択肢1)。



インシデント報告は、チームで支える大切な仕組みだと理解して解いてみてくださいね。
\看護師の靴は3カ月が寿命/
看護師の靴は、体以上に疲弊しています。私の経験上、ニオイや靴底のすり減りなどを考えると3カ月が寿命…ムレが少なく、クッション性のある靴がおすすめです。
  | 価格:2990円 |
インシデントへの正しい理解が、自分も患者も守る
インシデントは、誰でも経験する可能性がある「事故に至らなかったミスや問題」です。
報告は怖く感じますが、患者さんの安全を守るために、チーム全体で再発予防に取り組むためには欠かせません。
国家試験では、単なる定義の知識だけでなく「その場でどう行動するか」「どのように共有するか」が問われます。
日ごろから「もし起きたらどうするか」をイメージし、落ち着いて行動できるよう準備しておくことが大切です。
- インシデントは「事故に至らなかったが、問題があった事例」
- 分類レベル0〜3aがインシデント、3b〜5はアクシデント
- 報告の目的は「原因究明」と「再発防止」
- 報告は速やかに行い、チームで共有する
- 医療安全管理者が全体の安全体制を支える大切な役割を担う
- 国家試験では「報告の目的」「分類」「現場対応」が頻出



国家試験でも「なぜそうするのか」を考えて選択肢を選ぶと、自信を持って解答できますよ。
このブログが、あなたの国試対策や将来の実務に少しでも役立てば嬉しいです。
焦らず、一歩ずつ進んでいきましょうね。
応援しています!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
\都心部の病院と地方の給料差は10万円/
関東や関西、大きな都市は、地方と比べると10万円差があるのをご存じですか。私は、地方に住んでいるので都心部から帰ってきた看護師たちは「給料が10万違う…」と嘆くことも。自分自身で、優先事項を決めて就活しましょうね。

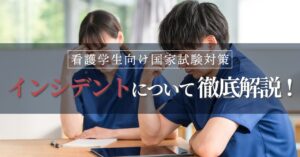


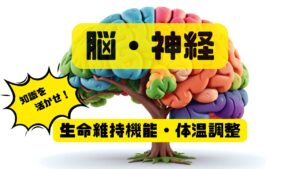

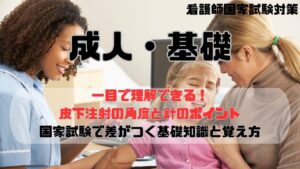
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] あわせて読みたい 看護師はインシデントが怖い?徹底理解!国試と現場で活きる基礎知識&過去問解説 このページのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています。 インシデン […]